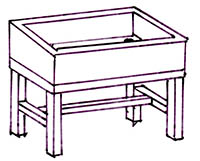台所(現在はキッチン)を構成するもののうち、「水回り」に属するのは流し台、給水栓または水がめ、排水管または排水溝である。
3-1 流し
各戸の台所の流しは、江戸時代まで「座り流し」といって床面におかれていた。明治時代になるとこれが土間や板の間の台におかれた「立ち流し」に変わった。だから私達が知っている流しは立ち流しである。深さ20cm程度、横幅60~90cm、奥行き60cm位の箱で片隅に穴が開けられ、水が流れ落ちるようになっている。素材は木材かそれに銅板や亜鉛引き鉄板をカバーしたもの、または「人研ぎ」といって粗めの砂を入れたモルタル製の箱の表面を削り、研いだものが使われた。これは今も学校の屋外水飲み場等で使われている。人研ぎで大理石砂を使ったものは「テラゾー」と言われた。
3-2 水甕(みずがめ)
水道のない所(時代)では炊事用に使う水は井戸からくみ上げて甕に蓄え、柄杓(ひしゃく)で汲んでは調理や食器洗いに用いた。水甕は素焼き壺に防水のため釉薬(うわぐすり)をほどこして焼いたもので、30~50リットルくらいの容量があった。水を汲む時以外は木製の蓋が被せられている。蚊が入ってボウフラが発生しないようにするためである。水は勿論井戸から汲む。場所によっては川水を汲むこともあった。
3-3 水栓蛇口
蛇口(カラン)は水道管と連結しており、ハンドルをひねれば水が噴き出す。人力で水をくみ上げ、運ばなくても片手でハンドルをひねるだけで清澄な水が得られるわけで、大変な生活様式の向上であった。カランは当初自治体の水道当局が指定するものだけであったが後にアートデザイン様式の製品も使用されるようになった。自治体当局の中には、「節水コマ」といって水の通り道を小さくしてカランからの吐出水量をセーブするものが人気を集めた。
3-4 排水の行方
流しで捨てられた水はどこに行くのか。戦前、大都市でさえも下水道は殆ど設置されておらず、流しや風呂場からの排水は排水管を通じて道路側溝や水路に排出されるか、排水だめに流されていた。東京の多摩地区では、排水だめは井戸と同じように地中をくりぬき、水が浸透するようにしたものであった。飲み水用の井戸とは一定の距離(15~20m)を保つように掘られているが今から考えると衛生上極めてリスクが高いものであった。
【関連】
3-5 竈(薪釜、炭コンロ、練炭コンロ、ガスコンロ)
炊事には煮(に)炊(たき)が伴うが、東京郊外ではまだ都市ガスやプロパンガスはなく、加熱には、竈やコンロが使われていた。竈の事を農家等では「へっつい」とよんだ。竈を「へ」と読み、「竈つ火」からきているという。竈には乾燥した木材(薪)が使われ、コンロには炭や練炭、豆炭が使われていた。関西では「おくど」さんという。
薪や炭は専門の販売店があり、配達して貰らったり、自分で買い取りに行った。薪は燃えやすくするため細材に割る必要があった。この薪割りは通常、大人(成人男子)の仕事であったが小学生の男の子にもその仕事が課せられた。だから当時の男の子は、小さい時から「斧」とか「鉈」を使う術は身につけるようになっていた。コンロにしても、紙くずを燃やし、細材(割りばしのごとき)に火をつけ、その火力で炭に着火させる。そうしたことも当時の子供は小さい時からやらされていた。練炭や豆炭にしても同じである。逆にガスコンロは慣れていないので、マッチを擦って着火する動作が怖かった。
|
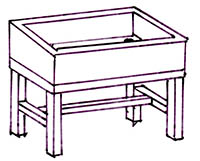


かまど
煙突が備えられ、やや近代化したかまど |
3-6 :薪から「消し炭」の回収そして着火材としての利用
ガスが入っていなくて、電気釜も発明されていない頃、ご飯を炊くのは鉄ないしアルミ鋳物製の羽根突き釜であった。これを竈の上に掛け、下から薪を燃やして加熱する。火加減は「はじめ、チョロチョロ、なかパッパ、赤児泣いても蓋取るな」とあるように飯炊きにはコツが要った。つまり薪のくべ加減を調節し、終りの方では炎が消えているけれど炭の状態を保っている燃えかすを引き揚げてしまう必要があった。燃えかすは「消し壺」に移し、「消し炭」を作っていた。燃えかすは壺の中で空気が遮断されると其のまま炭の状態で冷えて行く。消し炭はコンロで火起こしする時、すぐ火が付き着火助材として便利に使われた。
|